「発達障害」って最近よく聞くけど、いったいどういうもの?
自分は「発達障害」?だとしたらどうしたら良い?
「発達障害」の当事者とのつきあい方は?
そんな悩みに応える1冊です
この本は、「発達障害」の中でも「アスペルガー症候群」と「ADHD」を中心に、特徴とつきあい方が
わかりやすく解説されています
監修:星野仁彦(Hoshino Yoshihiko)さん
この本の監修者は、「星野仁彦」先生です。
1947年福島生まれ。1973年福島県立医科大学卒業。米国エール大学児童精神科留学。福島県立医科大学神経精神医学講座准教授を経て、現在、福島学院大学福祉学部福祉心理学科教授、副学長をされています。大人の発達障害や児童精神医学分野の第一人者で、他に精神薬理学なども専門とされています。
42歳の時、大腸ガン、転移性肝臓ガンを、「星野式ゲルソン療法」で克服。福島県郡山市にある「ロマリンダクリニック」で心療内科、ガン患者のカウンセリングを担当。「発達障害に気づかない大人たち(2010・共著・祥伝社)」「なんだかうまくいかないのは女性の発達障害かもしれません(2015・共著)」「ガンを食事で治す星野式ゲルソン療法(5年生存率0%からの生還)(2017年・共著)」など他にも多数の著書があります
監修者経歴参考資料
- 星野仁彦監修(2012)『それって「大人の発達障害」かも?正しい理解と上手なつきあい方』大和出版
- 星野仁彦プロフィール | ロマリンダクリニック (lomalinda-jp.com)
アスペルガー症候群
「周囲になじめない、空気が読めない……」という悩みがあるなら、まずこの部分を読むことをおすすめします
アスペルガー症候群は「自閉症スペクトラム障害(ASD)」というものに分類されるとのこと
知的能力・言語能力は高く、「こどもっぽさがある反面天才的な能力も発揮する」という特徴があるようです
アスペルガー症候群の特性は5つにまとめられています
①「対人関係をきずくことが得意ではない。もともと人と親しくなりたいとは思っていないから親しい人がいないことがつらくはない」
②「言葉によるコミュニケーションが得意ではない。相手の話題に興味が無いため会話がドッジボールになる」
③「こだわりが人一倍強い。一つのことに『ハマる』と周りが見えなくなる」
④「感覚が異常。五感が異常に敏感だったり、異常に鈍感だったりする」
⑤「協調運動が苦手。縄跳びやボールを投げる・とる、手先の運動(折り紙やはさみの使用など)も苦手」
言語・知的能力に遅れがあまりないことで幼い頃には見過ごされてしまうこともあるようです
何か当てはまる症状があって不安に思う・悩んでいる場合は、専門の機関で受診してみることも解決の一つの手段になりそうですね
ADHD
「忘れ物が多い、片付けができない……」という悩みがあるのなら、この部分を読むことをおすすめします
ADHD(Attention Deficit Hyper-activity Disorder)は日本語で「注意欠陥・多動性障害」と訳されるものです
「不注意」や「多動」など行動面が強調されて伝わりますが、実際には社会性・認知機能・運動機能など様々な能力の発達がアンバランスのため、社会適合の問題になっているとされています
そのためこの本では、「発達障害」は「発達アンバランス症候群」と呼ぶほうがADHDを正しく理解できると述べています
ADHDの特性は8つにまとめられています
①「管理することがとても苦手。全般的に不注意で集中力がないが、自分の興味があること・関心があることに関しては過集中となる」
②「落ち着きがなくじっとしていられない。子供の頃は全身の多動があり、大人になるにつれ全身の多動は落ち着くけれど、心の多動が残る」
③「衝動性の制御が苦手。大人になっても治らない特性で、思いつきで行動するため周囲の人達に迷惑がかかり、しんらいかんけいがくずれてしまうこともある」
④「期限が守れず、自分を責めてしまう。うっかり忘れたり、自分の興味のあることばかりを優先してしまう」
⑤「感情のコントロールが苦手。思い通りにいかないとキレたり、気分が落ち込んだりする」
⑥「成功体験の少なさや自分の客観視が苦手。ストレス耐性が低く、とても心配性でいつも強い不安感にとらわれている」
⑦「共感性が欠如している。相手の気持が読めず怒らせてしまうため孤立してしまう」
⑧「退屈に耐えられず、常に新しい刺激を追い求め、独創性を持つ。飽きっぽく忍耐力がないが
独創的な仕事で才能を発揮する可能性もある」
子供の頃から目に見える症状として現れやすい特性がおおいようですが、あらわれる症状やその程度は人それぞれです
他にも「随伴症状」と呼ばれる症状もあるようなので、ぜひ実際に書籍を読んでいただきたいです
「発達障害」を理解・治療
「発達障害」ってどこか遠いもののように感じていませんか?
2002年に文部科学省が日本全国各都道府県の公立小中学校を対象に行なった調査結果によると、発達障害の可能性がある児童の割合は「6.5%」と報告されています
30人1クラスの学級で例えると、1クラスに2~3人は発達障害の可能性がある児童がいることになります
ただこのデータは通常学級の小・中学校の子供が対象のため、特別支援学級に通う子供が入っておらず、実際にはもっと多くの割合となると考えられます
さらに、2008年度以降は毎年6000人ずつ増加しているというデータもあるようです
これらの増加の要因としては、2005年に「発達障害者支援法」が施行され、医療関係者を始め保健・福祉関係者、保育士・教師「発達障害」が広く認識されるようになったこともあるようです
広く認識されるということは、それだけ症状に不安を覚え受診する人が増えるということですから、相対的に発見も増えるということですね
子供の頃は発見されず、大人になってから対人関係で悩んで受診し「発達障害」が明らかになるケースも少なくないようです
「発達障害」の理解として、「生物学的要因」「心理社会的要因」「アスペルガー症候群やADHDの以外の発達障害」と言った項目があります
そしてその治療として、「受診」「心理教育・環境調整療法」「薬物療法」「心理療法・認知行動療法」が解説されています
似ている病気や併発しやすい病気もあるため、正確な診断が有効な治療にはとても大切と言えそうですね
本人や周囲ができる「生きにくさ」を減らすためのひと工夫
最後は、協調性が重視され「発達障害」の人が「生きにくさ」を感じる現代日本で、「生きにくさ」を減らすために何ができるかです
本書籍では、「発達障害」の人が社会に受け入れられるためには本人が適切な治療を受けることに加え、周囲のサポートが必要不可欠であると述べています
したがって、「時間が守れない」「物忘れが多い」など、11個の「困った!」について、それぞれどのように本人や周囲が対処すればよいのかがアドバイスされています
興味や関心からこの本を読まれてもっと詳しく知りたくなったという方は、星野先生の別の書籍を読まれることをおすすめします
また、「アスペルガー症候群」や「ADHD」以外の「発達障害」についての書籍や情報についても検索するとすぐ触れることができますので、ぜひ新しい情報を仕入れていただければと思います
おわりに
ぜひ実際にこの書籍を読んで気になる項目について学んでいただければと思いますが、いずれにしても「発達障害」についての正しい知識と治療法・対処法を知ることがとても大切だと思います
「大人の発達障害」は世界的にもまだまだデータや統計が少ないようですので、今後もっと新しい情報が出てきたり認識が変化したりするということも考えられます
今知った情報が全てと思うのではなく、認識や常識は時代や時間の流れで変わることがあると思って学び続けていくことが大切と思って、ゆるなつも学びつづけていきます
一緒に学んでいきましょう







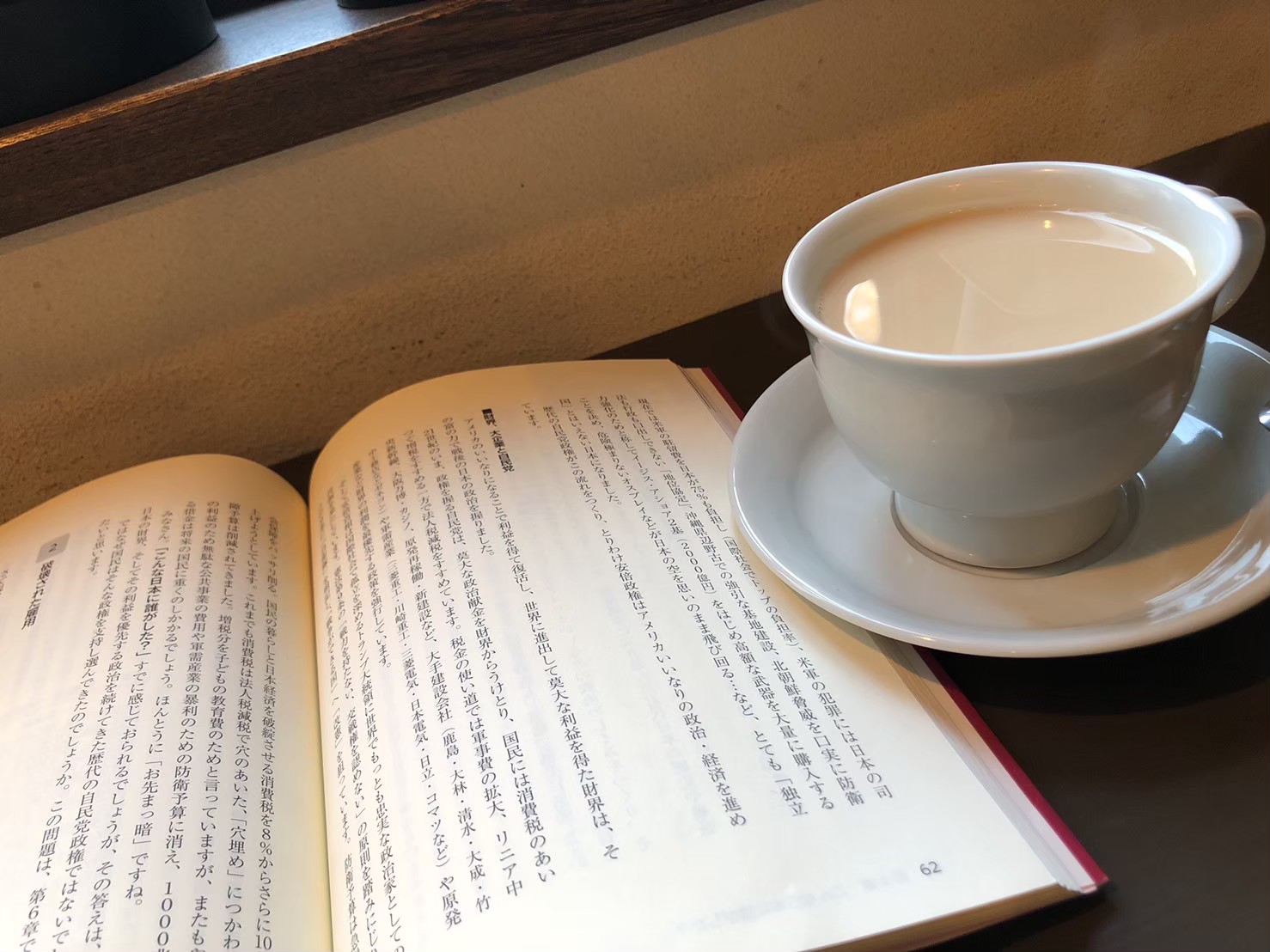

コメント